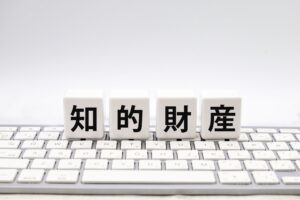【オープンイノベーションと知財】大学・他社との連携の落とし穴
〜「共同出願ってどうなるの?」という素朴な疑問に答えます〜
近年、「オープンイノベーション」という言葉をよく耳にするようになりました。
スタートアップや中小企業が、大学や大企業と手を組み、新たな技術開発や事業創造に挑戦する機会が増えています。 しかし、この前向きな連携の裏側には、**“知財の落とし穴”**が潜んでいる可能性があることをご存じでしょうか?
今回は、実際によくご相談いただく「共同出願」や「知財契約」にまつわる疑問にお答えしながら、連携時に注意すべき5つのリスクとその対策を解説します。
リスク1:「共同出願」は単独行動を阻害する
共同出願とは、複数の当事者が共同で特許出願を行うことです。 例えば、貴社と大学の研究者が協力して新しい技術を生み出した場合、それぞれの「発明への貢献度」に応じて、特許の権利者(出願人)を共有する形になります。
しかし、安易な共同出願は、その後の事業展開に大きな制約をもたらす可能性があります。
- 単独でのライセンス許諾が不可: 他社に自由にライセンスすることができません。
- 単独での実施(使用)が不可: 自社だけで自由に技術を使うことができません。
つまり、何かを行う際には、必ず相手の同意が必要となるため、事業化のスピードや柔軟性が大きく損なわれるリスクがあるのです。
リスク2:「誰が何を出すか」を曖昧にしたままスタート
「まずは一緒にやってみましょう!」という勢いで始まるプロジェクトにありがちなのが、成果物の権利の帰属を後回しにしてしまうケースです。 その結果、
- どこまでが自社の独自のアイデアなのか?
- 発明者として誰の名前を挙げるべきか?
- そもそも特許出願をするのか否か?
といった根本的な部分で、後々大きなトラブルに発展してしまうのです。初期段階での認識のずれが、深刻な対立を生む典型的なパターンと言えるでしょう。
リスク3:企業と大学の知財に対する文化の違い
大学との連携においては、企業と大学とで知財に対する考え方が大きく異なる場合があります。
- 企業: 利益の確保、独占的な実施を重視
- 大学: 研究成果の公開、学術的な発表を重視
この点を十分に理解し、事前にすり合わせを行わないと、**「先に学会で発表してしまい、結果として特許が取得できなくなる!」**といった事態を招きかねません。せっかくの革新的な技術が、発表によって公知となり、権利保護の機会を失ってしまうのです。
では、この文化の違いを乗り越えるためにはどうすれば良いのでしょうか?
- 事前に秘密保持契約(NDA)を締結し、情報開示の範囲を明確化する。
- 知財に関する協議の場を定期的に設け、両者の認識のずれを解消する。
- 研究成果の公表時期について、特許出願の準備期間を考慮して合意形成を行う。
リスク4:不十分な契約書が紛争の火種に
共同出願や共同研究を行う際には、共同研究契約書や秘密保持契約書などの契約書をしっかりと整備することが極めて重要です。 特に、以下の項目については、曖昧なまま進めてしまうと、後々、権利関係や費用負担に関する深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。
- 発明の帰属: 誰がどのような貢献をして、成果の権利を誰が持つのかを明確にする(曖昧な場合、成果の取り合いが生じる可能性があります)。
- 出願・管理の方針: 特許出願の手続きや費用負担、拒絶理由通知への対応、登録後の権利維持など、誰が責任を持って行うのか、費用をどのように分担するのかを明確にする(責任や費用分担が不明確だと、出願自体が進まないこともあります)。
- 実施・ライセンスの権利: 共同で得られた特許を、各当事者がどのように実施できるのか、第三者にライセンスする場合の条件などを明確にする(自社が自由に技術を活用できなかったり、ライセンスによる収益化が困難になったりするリスクがあります)。
- 公表・学会発表の扱い: 研究成果をいつ、どこまで公開できるのか、特許出願との関係について明確なルールを定める(特許取得の機会を失う可能性があります)。
まとめ:オープンイノベーションの成果を「自社の武器」にするために
せっかくのオープンイノベーションも、知財に関する事前の検討を怠ると、その成果を十分に活かせないばかりか、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性すらあります。
逆に言えば、プロジェクトの初期段階から「出口」、つまり事業化を見据え、適切な知財戦略を策定し、関係者間で合意形成を図っておくことで、共同で生み出した知恵をしっかりと「自社の武器」に変えることができるのです。
「技術的には素晴らしい話なのに、知財の問題がネックとなって前に進めない…」
このようなもったいない状況に陥らないためにも、オープンイノベーションに取り組む際には、知財の専門家へのご相談をぜひご検討ください。戦略的な知財マネジメントこそが、オープンイノベーション成功の鍵となります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
🧑💼 黒川弁理士事務所|代表 弁理士 黒川陽一(京都)
📩 初回30分無料!お問い合わせはこちら
🌐 スタートアップ・中小企業の経営に役立つ知財情報を発信中!
【関連キーワード】 #オープンイノベーション #共同出願 #知財契約 #スタートアップ #中小企業 #知財戦略 #特許 #大学連携 #技術開発 #京都弁理士 #黒川弁理士事務所