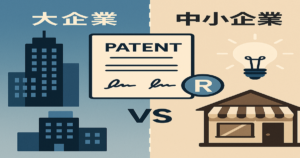ChatGPTのジブリ風画像生成は著作権侵害?話題のAIイラストと法的リスク
最近、AIが生成するスタジオジブリのような美しいイラストがSNSなどで大きな話題になっていますね。手軽に夢のような風景や温かいキャラクターが生み出せる一方で、「これって著作権的に大丈夫なの?」と疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この注目のAI画像生成と著作権の関係について、初めての方にもわかりやすく解説します。
「ジブリ風」という表現スタイルと著作権
スタジオジブリの作品は、独特の色彩、優しいタッチ、魅力的なキャラクター、そして心に残る世界観で、多くの人々に愛されています。これらの要素が合わさって「ジブリ風」という、誰もがイメージできる表現スタイルを確立しています。
では、この「ジブリ風」という表現スタイルをAIが学習し、似たような画像を生成することは、著作権法に触れるのでしょうか?
結論から申し上げますと、著作権法は、アイデアや表現スタイルといった抽象的な概念そのものを保護するものではありません。 著作権が保護するのは、具体的な絵画、映画、キャラクターデザインといった個々の創作物なのです。
「悲しい物語」というアイデアや、「水彩画」という描画手法が誰かの独占にならないように、「ジブリ風」という表現スタイルも、それ自体が著作権で保護されるわけではない、と考えるのが原則です。
著作権侵害が成立する2つの要件
AIが生成した画像が著作権侵害と判断されるためには、一般的に以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 類似性(るいじせい): 生成された画像が、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を共通に有すると認められること。
- 依拠性(いきょせい): 生成された画像が、既存の著作物(例えば、特定のジブリ作品のキャラクターや背景画像)を知っており、それをもとにして創作されたと認められること。
一つずつ、もう少し詳しく見ていきましょう。
1.類似性:表現の「本質的な特徴」が似ているとは?
類似性とは、生成された画像と既存の著作物とで、表現において重要な部分が似ているかどうかを判断するものです。
- アイデアではなく表現の類似: 著作権はアイデアを保護するものではないため、物語の筋やキャラクター設定などが似ていても、具体的な絵の表現が異なれば、類似性があるとは言えません。
- 「本質的な特徴」の重視: 著作物の全体的な印象だけでなく、その創作性の中核となる部分(例えば、キャラクターの顔の輪郭や目の形、背景の独特な雰囲気など)が似ているかが重要になります。細かい部分が異なっていても、全体として受ける印象が元の著作物と変わらない場合、類似性が認められる可能性があります。
- ありふれた表現は考慮しない: 誰でも思いつくような表現や、一般的な表現方法は、類似性の判断においては考慮されません。例えば、風景画に木や空が描かれていることは、ありふれた表現であり、類似性の根拠にはなりにくいです。
2.依拠性:既存の著作物を「知って」「もとにした」とは?
依拠性とは、簡単に言えば「真似をした」ということです。ただし、法律の世界では、単に似ているだけでは依拠性があるとは言えません。
- 既存の著作物の存在と認識: まず、著作権で保護されている既存の作品が存在し、その作品を生成した人が知っていた(認識していた)必要があります。AIの場合、学習データに著作物が含まれていることが、この認識があったと推定される根拠の一つになることがあります。
- 既存の著作物に基づく創作: 生成された画像が、既存の著作物の表現を取り入れている必要があります。これは、単にアイデアが似ているだけでなく、具体的な表現(線の使い方、色の選び方、構図など)において影響を受けていることを意味します。
もし、AIが偶然、既存のジブリ作品と似たような画像を生成したとしても、その作品を知らずに、また影響も受けていないのであれば、依拠性は認められません。
AIと著作権:現時点での考え方
ChatGPTのようなAI画像生成ツールは、インターネット上の膨大な画像を学習データとして利用しています。その中には、スタジオジブリの作品も含まれている可能性はあります。
しかし、現時点では、多くの場合、AIは学習したデータから、ジブリ作品に共通する表現の傾向を抽出し、それを元に新たな画像を生成していると考えられます。
そのため、生成された画像が、特定のジブリ作品の具体的な表現に依拠しておらず、単にその作風を参考にしたに過ぎない場合、直ちに著作権侵害となる可能性は低いと考えられます。
ただし、本質的な特徴が似ているレベルにまで、キャラクターや背景などを再現してしまうと著作権侵害のリスクが高まってしまうために注意が必要と考えられます。
利用する上での注意点
AI画像生成ツールを利用する際には、以下の点に注意することが大切です。
- 利用規約の確認: 各AIツールの利用規約には、生成された画像の利用範囲や著作権に関する規定が定められている場合がありますので、必ず確認しましょう。
- 商業利用の検討: 生成された画像を商用目的で利用する場合は、著作権侵害のリスクが高まる可能性があります。専門家(弁護士・弁理士など)に相談することをおすすめします。
- 特定の作品への過度な類似を避ける: プロンプト(指示文)を工夫したり、生成後の画像を修正したりすることで、既存の著作物との類似性を低減する努力をすることも重要です。
まとめ:AIと著作権、正しく理解して活用を
AI技術は、私たちの創造性を刺激する素晴らしい可能性を秘めています。著作権のルールを正しく理解し、AIと上手に付き合っていくことが、これからの時代においてますます重要になってくるでしょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
もし、AIで生成した画像の利用について不安なことや疑問点があれば、お気軽に弁理士にご相談ください。
🧑💼 黒川弁理士事務所|代表 弁理士 黒川陽一(京都)
📩 初回30分無料!お問い合わせはこちら
🌐 スタートアップ・中小企業のための経営に役立つ知財情報を発信中!
#ChatGPT #AIイラスト #画像生成 #ジブリ風 #著作権 #類似性 #依拠性 #知的財産 #弁理士 #AIと著作権